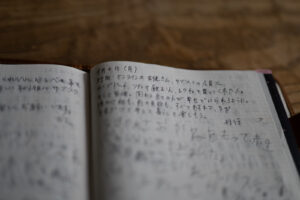朝、梨の共同防除のために、地域のメンバーと一緒に機械のオペレーターをしていたときのこと。
突然、パジャマ姿の息子が畑にやってきた。
「ゴミ捨てに行ったらさ、大きい音が聞こえてきて。なんか気になって」
僕がいるかどうかなんて関係なく、ただ“気になったから”ふらふらと歩いてきたその姿に、思わず笑ってしまった。
「梨に虫や病気が出ないように、薬を撒いてるんだよ」と説明すると、息子は興味津々で、機械が動く様子をじっと見つめていた。
ちょうどそのとき、僕は交代で地上にいて、ペアの方が運転中。
機械が近づいてくると、息子は手を振った。
「プップッ」とクラクションを鳴らしてくれたペアに大喜びで、そのまま嬉しそうに家に戻っていった。
薬剤が切れて補充していたとき、ペアの方がふと言った。
「もう帰しちゃったの?夏休みなんだし、止まってる間だけでも乗せてあげればよかったのに」

数分後、軽トラが戻ってきた。助手席には、さっきのパジャマ姿の息子。
手にはなぜか家にはないポカリスエットのペットボトルを持ち、表情は得意げ。
僕がオペレーターとして操縦している様子を、助手席からじっと見ている。
その光景はまるで、「理想の田舎」とでも名づけたくなるようなワンシーンだった。
“地域に育てられる”という感覚。
こうして誰かが気にかけてくれて、ちょっとした冒険が生まれる。
そういう“当たり前”が、地域にはある。
SNSではよく、
「田舎に移住したけど、自治会費とか払いたくないから自治会には入らない」
「ゴミステーションだけ使ってる」
なんて投稿を見る。
でも、僕にはそれが本当に遠い世界の話に思える。
回覧板を持っていってお菓子をもらって帰ってくる息子、
ご近所さんに「おはよう!」と挨拶する息子、
なぜか道端でもらった大きなきゅうりを片手に帰ってくる息子。
そして、普段は触れることのない機械に、そっと乗せてもらえる息子。
こんな日常は、その地域の中にきちんと根を張って、
人と人との間に信頼があるからこそ、生まれるものだと思う。
僕が息子によく言うのは、
「お勉強ができるより、挨拶がちゃんとできる方が偉いよ」という言葉。
それをそのまま信じてくれているのか、学校でも、家でも、登下校中にすれ違った人にも、息子はきちんと挨拶をする。
個人面談では、先生がこう言ってくれた。
「咲多くんが教室に入ってくると、大きな挨拶してくれるからパッと明るくなるんです」って。
勉強なんて、大人になってからでもできる。
でも、地域に愛されて育つという経験は、人生の根っこになる。
それは、お金には決して代えられない「豊かさ」なんじゃないかと思うのです。
そしてその豊かさを、ちゃんと分かってくれている息子を、僕は心から偉いと思っている。
台所もまた、小さな地域のようなもの。
食卓を囲む時間の中に、子どもが感じる愛情や記憶はきっと育っていく。
わたしたちの料理教室では、そんな「根っこ」を大切にしています。
家族の時間を、やさしく整えたいあなたへ。
よかったら、一度のぞいてみてください。
▶︎ waktak cooking class|月額オンラインレッスンはこちら