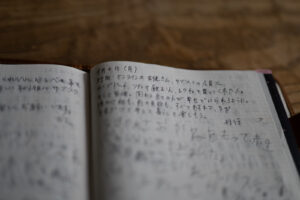―「食べる人」から「作る人」へ ―
ジョンは、いつも食卓に並んでいた。
ズッキーニのジョン、
トウモロコシのジョン、
ジャガイモのジョン、
白菜のジョン。
それぞれが季節の香りをまとい、その時その時の“旬”を並べる料理だった。
とても庶民的で、とても贅沢な料理
ジョンという料理は、決して派手ではない。
けれど、どの食材もひとつひとつ衣をつけて丁寧に焼くという手間のかかる料理だ。
庶民的でありながら、作る人の手間と想いが詰まった、実はとても贅沢な料理なのだ。

ハレの日のジョンは、
まるでごちそうだった
でも、そんなジョンも“ハレの日”になると少し変わる。
カラフルな「オミサンジョン」(五色のジョン)。
牛肉や魚を使った、特別なおかずたち。
ふだんは野菜が中心のジョンが、その日ばかりは高級料理のように見えた。

子どもの頃の私の役割は「食べる人」
子どもの頃の私は、ただただ食べる人だった。
台所では、母と姉がせっせとジョンを焼いていたけれど、私はただ、焼きたての香りに心を踊らせる係。
ハレの日のジョンたちは、いつもより少し豪華で、少しカラフルで、見るだけで心が躍る料理だった。
それがハレの日料理のマジックだと思う。
姉の言葉と、今の私
今でも姉は、私に会うとこう言う。
「あんたが料理するなんて信じられない。」
それくらい、私はずっと「食べる人」だった。
それなのに今、私は料理教室の先生になっている。

食の記憶は、強く残る
小さい頃の食卓の記憶というのは、不思議とずっと残っている。
あの時のジョンの味、色とりどりの見た目、母や姉がキッチンで立ち働く姿。
それらが、今の私の「味覚の土台」になっている。
今は、私が「作る人」
私は今、料理を作っている。
そして、「食べる人」ができた。
それは、家族だったり、生徒さんだったり、キッチンカーに来てくださる方だったり。
私にも、誰かのごちそうになれる役割ができたのだ。
幸せなことじゃないか
「食べる人」だった私が、今は「作る人」になっている。
小さい頃、母と姉がやっていたことを、今、私がやっている。
それって、とても幸せなことじゃないかと思うのだ。
だから私は、今日もジョンを焼こうと思う。
季節の色と香りを感じながら。