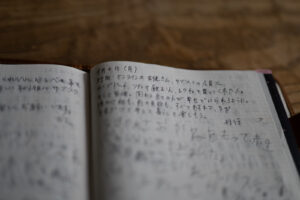「お母さんの料理、最後に一緒に作ったのはいつですか?」
そんな問いかけに、少し戸惑ってしまう人もいるかもしれません。
私も、つい最近まで思い出せませんでした。
でも今日は、母と一緒に饅頭を作りました。
目分量と「大丈夫」のあいだ

両親は今、二人暮らし。
中国の故郷では毎朝、饅頭とお粥、そして搾菜を一緒に食べているそうです。
私も母に習ってその饅頭を作ってみることにしました。
「中力粉が一番いいよ」
と、父がぽつりとアドバイス。
そして母は、なんのためらいもなく、目分量でイースト菌を投入。
「ちょっと、それ大丈夫ですか…?」
思わず何度も聞いてしまった私に、母は笑って言いました。
「体で覚えてるから、大丈夫」
それはどこか、信仰にも似た安心感がある言葉でした。
私はまだ、すぐにレシピを確認しようとするけれど、母は自分の手と記憶を信じている。
この差がきっと年月なのだろうなと思います。
塩も砂糖も「いらないよ」
「塩と砂糖、入れた方がよくない?」
と私が言うと、母はきっぱりと首を横に振りました。
「搾菜があるでしょ。あれがあるから、調味料はいらないの」
私にとっては、味付けのない饅頭というのは少し不思議な感じ。
でも母にとっては、それがいつもの味、いつもの朝。
具を入れるでもなく、何かを飾るわけでもなく、ただただ粉と水と酵母でできた饅頭。
「それでいいんだよ」
母の声には、どこか哲学のような重みがありました。
発酵の時間と、記憶の時間

一次発酵は3時間。
「えっ、そんなに!?」と私が驚くと、母は笑いながら「それが普通だよ」と言いました。
時間をかけて膨らんでいく生地。
ふっくらとした姿になった頃、母と一緒にそっとガスを抜きました。
「2次発酵は…」
と聞く私に、「だいたいこのくらい」とまた目分量。
「均等にしなくていいの?」
「ラードは使わないの?」
私の頭の中の常識が、どんどん母の言葉で壊されていきます。
でもそのたびに、不思議とワクワクしている自分がいました。
蒸し器から立ちのぼる湯気と、母の手の味

「蒸し器には、水から入れるんだよ」
と母が言いました。
それも私にとっては新しい知識。
火を入れてから15分、そして5分休ませて蒸し器の蓋を開けたとき、
そこにはふわっと膨らんだ、ころんと可愛らしい饅頭たち。
湯気の向こうに、昔の母の手元が重なります。
ひと口食べるとそれはもう、言葉にできないくらい懐かしく、温かい味。
噛めば噛むほど胸がいっぱいになるあの食感。
「母の味ってこういうことか」
と、心の中でそっとつぶやきました。
具がないから、想像できる味がある

その饅頭には具がありません。
ただの「生地だけの蒸しパン」。
でも、搾菜と一緒に食べると、ちゃんと「食事」になる。
何より驚いたのは、具がないからこそ、たくさんの味を想像できたこと。
噛んだときに感じる香り、もちもちとした食感、じんわりと広がる小麦の甘さ。
すべてが母の手のひらから生まれた味でした。
レシピにはない、記憶の継承

コンビニの肉まんとはまったく違う。
いや、比べることすらできない。
そこにあるのは、調味料でも技術でもなく、「誰かのために」という手の記憶。
だからこそ、こんなにも心に残るのかもしれません。
私は今日、母の饅頭を一緒に作ってみて改めて思いました。
この手から生まれる味を、少しずつでも受け継いでいきたいと。
「次は、あなた一人で作ってみなさい」
母がそう言った時、私はちょっと背筋を伸ばしました。
そしてそっと、母と同じように中力粉を手に取りました。
家庭料理に宿る「伝える力」
料理って、誰かに伝えることそのものだと思います。
それはレシピだけではなく、その人の経験や勘、そして何より「想い」。
今回の母との饅頭づくりは、ただの料理ではなく、手の記憶の継承でした。
料理教室では、きっちりと計量しながら教える私ですが、
その奥にある「目分量の愛情」も、大切に伝えていけたらと思っています。
そんな「想いのある料理」を、教室でもひとつずつ丁寧にお伝えしています。
今、季節のレッスンを募集しています。
▶ 詳細はこちらからご覧ください

両親との暮らしの中で、私はたくさんの学びがありました。
▶︎そんなことをそっと綴っています。